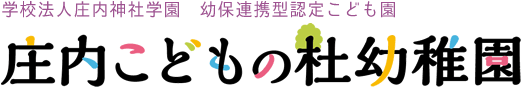TOPICS
園長通信(R7年4月号)
園長つぶやき~園関係者が「みんなのなかで、やりたいことをする人」に~
ご入園ご進級おめでとうございます。
昨年度は思い返すと天災・気候に頭を悩ませた一年であったと思います。
人類を含めすべての生物が、抗うことができない状況にいかに対応・適応していくかを、神様が試されているのではないかと思うような日々でした。
さて今回は、そんなVUCA(ブーカ)と言われる先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態を乗り切り、前に進むための決断力についてです。
情報過多で様々な価値観の人たちがいる社会では、困難な状況を乗り切るための施策や案を合意することがとても難しくなってきたと思っています。
ではどのように、これらの困難な状況を解決していくのか、以下の方法が基本です。
①問題の共有:何が問題かをみんなで否定せず出し合い原因を探る
②課題設定:問題を深掘りしてでた原因を解決するための具体的な活動を決定
③目的確認:最終みんながどうありたいかを具体的な言葉にして決める
④課題実行:課題を実行する5W1Hを明確にして実行
⑤進捗確認:実施状況を確認して、問題が起これば①に戻り立て直す
①~⑤の細かな解説は以前・今後の園長通信に譲らせてもらうとします。
ただ、それぞれの状況で何かを決めるにしても、様々な価値観の人たちの中で、合意していくことはとても難しいと思います。
以前の日本は、上司や先輩の命令を批判や否定することなく忠実に実行することを良しとする社会でした。しかし現代社会は一人のリーダーが強権的に決定することは減少し、参加者の合意形成を大切にしながら物事を決める時代です。
これが逆に、物事を進めることを難しくさせています。
決めるには、「選択」と「決断」の2種類の意味合いがあります。
選択:複数ある選択肢の中から、「今日の昼食はこの店にしよう」と、次回も選ぶこと が可能な内容を決めること。
決断:複数ある選択肢の中から、「わが社の販売方針をこれにする」と他の選択肢を捨 てて決めること。
これら二つの決めることに対して、失敗した後でも代わりがきく「選択」より、他を捨てた「決断」の方が、責任の重さが違いますし、個人レベルはなく複数人のチームで決定となると、それがなおさら重くなります。
正解があるものに対して決定することは、失敗してもすぐに修正できるから簡単です。
でも不確実な世の中で下した決定は、すぐに結果がわからないから困難です。
元ソニー社長の平井一夫氏が決めることに対してこんなことを言っています。
「一番よくないのは決断しないこと。なぜかというと間違えた判断をしたことに気付いたら、軌道修正をすればいいからです。」
決めることに必要なのは、『嫌われる勇気(岸見一郎)』に述べられている、決定結果によって非難されたり嫌われたりすることを恐れず、自分の信じる生き方を貫く勇気です。
当園の目指す姿「みんなのなかで、やりたいことをする人」になるには、単に仲良しではなく、個人やチームの目的・目標がしっかりと合意されていることが、その決定する勇気を生み出してくれます。
この一年、当園も大切にしている理念を基に、職員一同進んでいきたいと思います。
2025年4月1日