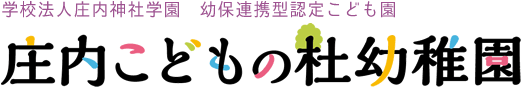TOPICS
園長通信(令和7年3月13日号)
園長つぶやき~園関係者が「みんなのなかで、やりたいことをする人」に~
急に春が訪れたかのような陽気の日々がやってきました。
次年度の学年をかなり意識した子どもたちを見ると、日々逞しさを感じます。
さて今回は、保護者会総会でお話しした、これからの社会を見すえて身に付けるべきことについてです。
令和6年(2024年)の出生数が約72万人で、またまた過去最低を更新したとの報道がなされていました。
ここ10年で出生数が30万人減り、将来子どもたちが働く時代の労働者人口が3割減となることは、変えようのない事実になっています。
USJの入場券売り場がなくなったり、イオンの無人レジが増加している現実が、企業は少子化に備えた対応を取りつつあることがうかがえます。
人が担っていた筋肉を使う労働をITで、脳を使う労働をAIが代価しつつあります。
そんな未来に残るといわれる新たなものを作り出す業務や、ヒューマンタッチと言われる人と接して対応する業務に必要といわれる力は、意欲とコミュニケーション力です。
人は必ず意欲を持って生まれてきます。
小さな子どもは、何度こけて膝を擦りむいても新たな発見をするために動き続け、出会った世の中の些細な事象に対して、「何で、どうして?」と興味を持って大人に聞きまわる力を持って生まれてきます。
大人は、その興味関心力を妨げることなく、上手く社会で発揮できるように育成すればよいと思っています。
一方のコミュニケーション力は、他人と接しながら育てるしかありません。
コミュニケーションは、人が人と活動をする限りずっとつきまとうものでありながら、 家族形態の変化(多世代での生活、兄弟の人数)や地域社会(子ども会、地域行事、自治会)の減少等、コミュニケーションを学ぶ機会は以前より極端に減っています。
アンジャッシュ渡部さんは、謹慎中に年200回の話し方講演を行っていたそうですが、様々な業種・企業で共通する悩みは、コミュニケーションギャップの問題だそうです。
サービス過剰な環境に慣れずっと受動的な姿勢で育ってきたヒトは、自分で考えて判断する力が育まず「やってもらって当たり前」の状況となり、「誰かの言うとおりにやった」のに良い結果が出ないと「うまくいかないのは〇〇のせい」と他責的になっていきます。
「コミュニケーション力が育たないのはその場が無いせい」と考えるかもしれません。
こんな子どもを取り巻く社会で、コミュニケーション力を育てる機会は、待っていても来ることはなく、園だけでなく保護者の皆さん自身が 多様な人たちと関わることができるコミュニティを自ら作ることが必要です。
これからは、多様な人々が協力し合いながら、新しい価値や社会システムを生み出していく共創(きょうそう)社会が求められます。
この共創社会は、単なる「共存」ではなく、互いの強みを活かして、より良い未来を築いていくことが特徴で、参加する人が主体性を持って取り組むことで実現します。
是非保護者の皆様も、共創社会を作る一員となってみてください。
2025年3月13日